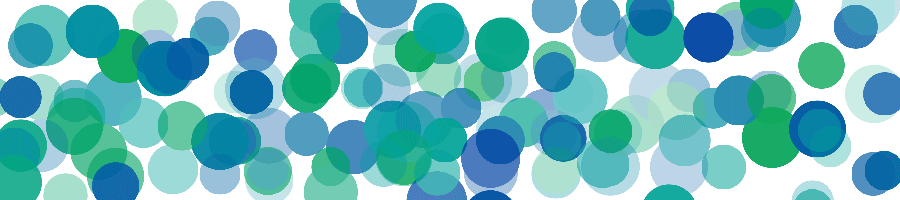8月30日

写真1 ( C ) ESA/Webb, NASA & CSA, M. Villenave et al.
ジェームズ・ウエッブ宇宙望遠鏡が捉えたおうし座星形成領域にある原始惑星系円盤・IRAS 04302+2247の姿。
ESAは29日、ジェームズ・ウエッブ宇宙望遠鏡(以下JWST)の赤外線観測データとハッブル宇宙望遠鏡(以下HST)の可視光データを組み合わせて作成された、おうし座星形成領域にある原始惑星系円盤・IRAS 04302+2247の写真を公開した(写真1)。写真左側で縦に黒い線が入っている部分が原始惑星系円盤であり、そこから左右にレインボーカラーで示された星雲があふれ出ている様子がわかる。蝶々のような形に見えることから、蝶々星とも名付けられている。
銀河のあらゆるところに星形成領域が存在するが、生まれたての赤ちゃん星は冷たいガスで構成された巨大星雲を作り始める。そして星が成長すると周りのガスを集め始め、そのガスが塵でできた原始惑星系円盤に集中するようになる。そしてこれらのガスや塵を基にして、惑星が作られ始める。このような初期状態の原始惑星系円盤を観測することは、我々が住む太陽系が最初どのような状態にあり、そこから太陽、地球、他の惑星がどのように形成されてきたかを研究する上で役立つ。
今回観測対象となった原始惑星系円盤・IRAS 04302+2247は、地球から約525光年離れた場所にあるおうし座星形成領域の中にある。中心に若い原始星が存在し、周りから塵やガスを集めており、周りにある原始惑星系円盤では惑星が形成途中にあると考えられている。
今回JWSTの近赤外線観測装置・NIRCamと中間赤外線観測装置・MIRIによる観測データとHSTの可視光データによって作成された写真1を見ると、写真左側に黒い縦の線が入っている部分があり、そこが原始惑星系円盤である。中心にある原始星は、黒い線によって隠れてしまいよく見えない。また原始惑星系円盤をフェイスオン(円盤を真上から見ている状態)で確認すると、渦巻構造が確認することができるが、今回の写真ではエッジオン(円盤を横から見ている状態)であるため、円盤の垂直構造を確認することができる。円盤の垂直構造を確認すると、円盤の厚みを確認することができて、どれくらい惑星形成能力があるかを確認することができる。また写真1では原始惑星系円盤から左右に明るい輝きを放っているが、これは原始惑星系円盤から左右に星雲が流れ出ており、原始星から放たれる光を反射した姿を表している。
今回の観測はWebb GO programme #2562と呼ばれるプログラムの一環で行われたものであり、4つのエッジオン原始惑星系円盤を調査することを目的としている。この観測によって、原始惑星系円盤において塵がどのように粒状になるかの理解が進み、惑星形成の理解が進むことが期待されている。